「リスキリング」とは何か
「リスキリング(Reskilling)」とは、技術革新や競合の動向等を踏まえ、市場の変化に速やかに対応し事業を継続的に成長させるために、従業員が新たなスキルや知識を習得し、再び学び直すことを意味します。単なる研修やスキルアップとは異なり、既存の職務とは異なる職種・領域へのシフトを前提とするケースが多く、企業全体の変革戦略の一環として注目されています。
経済産業省もリスキリングを「新しい職業への移行を前提とした能力開発」と位置付けており、今後の産業構造の変化に対応するために、個人・企業・国全体での取り組みが求められています。
企業がリスキリングを進める背景にある社会動向や課題感
リスキリングが注目されている背景として、急速に進むデジタル化と労働力不足という2つの大きな社会的課題があります。
1. DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の加速
AI、IoT、ビッグデータといったデジタル技術の進展により、あらゆる業界で業務の在り方が変わりつつあります。例えば、今日では、インターネットで注文したものが翌日に届くことを当たり前と感じている人も多いことでしょう。これは注文の受付~差配、商品の選定、集荷といったこれまで人手を介して実施していた一連のプロセスを自動化することによって実現しています。
あるいはそれによって、どこに住んでいる何歳の男性or女性が、何を、どれくらいの頻度で、どれくらいの価格帯のものを購入しているか、という購買データを収集することができ、これによってより消費者ニーズに即した商品開発やPRが可能となっているのです。
このように企業はこれまでのアナログ的な働き方から、データドリブンな意思決定や自動化を導入した業務プロセスへの転換を迫られており、それに対応できるデジタル人材の確保が急務となっているのです。
2. 労働力人口の減少と人材のミスマッチ
少子高齢化に伴い、特に日本国内では労働人口が減少し続けています。一方で、成長分野に必要なスキルを持った人材が不足しているという「ミスマッチ」が深刻化しています。例えば、エンジニアをはじめとするIT人材は、近年需要が伸び続けているものの、そういったスキルを有する人材は限定的で、市場での取り合いとなっています。
そのためそういった人材を市場から採用するのではなく、自社の既存社員を教育・育成し直すことで、自社内で供給できる体制を構築することは、ある種自然な流れと言えます。新たに新たな業務領域へシフトさせる「リスキリング」は、即戦力人材の確保に比べて、コスト効率が良く、組織への定着率も高いというメリットがあります。
3. キャリアの複線化・多様化
個人にとっても、終身雇用が崩れつつある現在、一つの職種に固執するよりも、複数のスキルや経験を持つことで市場価値を高める「キャリアの自律」が重要となってきています。リスキリングは、企業側だけでなく、社員自身のキャリア形成にも資する取り組みです。
リスキリングに取り組む企業の実例から学ぶ
ここでは、日本企業の中でも先進的にリスキリングに取り組んでいる事例をいくつか紹介します。具体的な実例を通して学ぶことは、よりイメージを具体化するのに役立ちます。
富士通株式会社:全従業員のDX人材化
取り組み背景
富士通は「ITカンパニーからDXカンパニーへ」を標榜し、業務のデジタル化・高度化を経営方針に明記しました 。
- 2020年度以降、5年間で5,000〜6,000億円規模の教育投資を実施
- 学習ポータル「FLX」を通じて9,000以上のオンライン教材を社員が自由に利用できる環境を整備
- ServiceNow/SAP/Microsoftと協業した「Global Strategic Partner Academy」を2021年12月からグローバル展開
成果と特徴
社外と連携した体系的な教育プログラムは、全従業員のデジタルリテラシー底上げに貢献。社員が自ら学ぶ文化を根付かせる仕組みとしても有効です。
サッポロビール株式会社:段階的DX育成と役割明確化
取り組み背景
グループ全体のDX推進には、非IT部門も巻き込んだ横断的な育成が不可避と判断し以下取り組みを展開しています。
- 全社員を対象にした「全社員ステップ」でIT・DX基礎をeラーニングで教育。
- 研修段階を明確化し、「サポーターステップ(中級)」、「リーダーステップ(上級)」など資格や業務で活用可能なスキル習得を促進。
- DXビジネスデザイナーやテクニカルプランナーなど職種定義を明文化し、具体的な成長パスを提示。
成果と特徴
単なる学びではなく「身につけたスキルをどう活かすか」にフォーカス。役割と学習の接続性を強化し、DXを経営基盤に据える狙いが鮮明となっています。
ENEOSホールディングス:レンタル移籍による異文化体験
取り組み背景
脱炭素や循環経済への転換期を迎え、社内だけでは得難い知見やスキル獲得が課題になっていることから以下取り組みを開始しています。
- 社員が1年間ベンチャー企業へ“レンタル移籍”し、実務を通じて新たなスキルや知見を吸収。
- オンライン学習プラットフォームを活用した継続学習環境の整備。
- 学習進捗・成果をKPIとして可視化し、経営陣に定期的に報告。
成果と特徴
社外の迅速な変化環境を経験させることで、新規事業への感度向上や風土醸成に効果。単なる学びではなく、体感による成長が得られます。
リスキリングの具体的な実施方法
では、企業がリスキリングを進める際、具体的にどのようなステップで取り組めばよいのでしょうか。一般的には、以下のような流れに基づき実施をしています。
1. 必要となるスキルの棚卸し・可視化
まずは、自社が今後必要とするスキルを明確化する必要があります。経営戦略・事業計画から逆算し、「どのような業務にどんなスキルが必要なのか」を定義します。例えば、DX推進を掲げる企業であれば、データ分析、プログラミング、プロジェクトマネジメントなどが該当します。
さらに具体的に言えば、いつ時点でいくらの収益を目標とするのか、それを実現するために、どういったスキルを有する人材がどれだけ必要となるのか、そういった人材ポートフォリオに基づきリスキリングの計画を立てることが望ましいといます。
2. 現在の従業員スキルの診断
次に、従業員が現在持っているスキルや経験を可視化します。これには、自己申告や上司評価、スキルアセスメントツールの活用などが用いられます。スキルギャップ(不足しているスキル)の明確化が、リスキリングのスタート地点です。
立ち上げ当初は中央集権的に、つまり会社主導でパワーをもって進めるのがよいでしょう。アンケート的に社員のスキルレベルを測定することはおすすめできません。なぜなら人によってそのスキル定義に対する解釈に揺らぎがあり、信頼できる情報とはならないためです。
そのためHRBPのような機能が、自組織の社員を一斉に評価するような横通し評価可能な仕組を用意することが重要です。HRBPについては以下記事で概要を紹介しています。
3. 学習プログラムの設計・提供
スキルギャップを埋めるための教育コンテンツを用意します。代表的な手法には以下のようなものがあります。大きく、業務を通じて育成するのか、業務外で育成するのか、の違いです。
いずれも重要で、どちらが良いというものではありませんが、私はeラーニングによる推進が最も重要であると考えています。なぜならば社員が自ら積極的に自学に取り組み、資格取得を目指すなど自走が最も期待できる手段であると考えているためです。
- 社内研修:自社業務に即した内容を独自に設計可能
- eラーニング:費用対効果が高く、自己主導学習にも最適
- 外部連携プログラム:大学・専門機関と連携した高度な教育
- OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング):学習と実務を並行して実施
4. 実践機会の提供と配置転換
学習したスキルを実務で活用する機会を設けることが、リスキリングの効果を最大化する鍵です。プロジェクトアサインや一時的な異動、クロスファンクショナルなチーム参加などを通じて、「学び」を「成果」につなげていきます。
一言で言えば「知識」を基に「実践」することで、手応えや自己肯定感を高めることが狙いです。
5. 成果の評価と継続的改善
リスキリングが実際の業務成果に結びついているかを評価します。個人レベルではパフォーマンスや成長度、組織レベルでは業績や離職率、社内公募応募数の変化などを指標にします。結果をもとに、教育プログラムの改善や配置の見直しを行うことが重要です。
上述の人材ポートフォリオと照らし合わせ、できたことできていないこと、振り返りと次の目標を設定すること、このプロセス化ができればリスキリングの仕組化は成功と言えるのではないでしょうか。
最後に
リスキリングは一過性の研修ではなく、経営戦略と人材戦略を連動させた中長期的な取り組みです。企業にとっては競争力強化の要、個人にとってはキャリア自律のチャンスとも言えるでしょう。
「何を学ばせるか」だけでなく、「学んだあとに何を任せるか」を含めた全体設計こそが、成功の鍵を握ります。社会や技術が変化する今こそ、企業と社員がともに未来を見据え、変わるための「学び直し」に本気で取り組むべき時なのです。





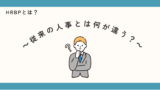


コメント