コーポレート人事としての限界
私は現在、縁あってコーポレート人事の業務に就かせていただいています。もともとは法人営業から始まったキャリアですが、そこでの実績をありがたいことに評価してくださる方がいて、その人に現在の人事部に呼んでいただいたのです。
昨今の激しい市場競争や、”大企業あるある”なベテラン社員の退職による社員減耗、そういった影響を受け弊社もこれまで注力していたメイン事業に陰りが見えてきており、数年前から新規事業の創出に複数取り組むとともに、一定勝ち筋の見えた事業に対しては、全社リソースをリバランスして事業を強化するなど取り組んできました。
一方でこれをコーポレート人事主導で実施することに違和感と限界を覚えたのも事実です。
コーポレート人事にいる限り、事業の実態が真に見えてこないのです。例えば、
- どのような業務フィールドに対し、どれだけの人数が現在従事していて、そこでできていること/できていないことは何なのか。
- 課題に対する解決策は見えているのか。あるいはどういったスキルや経験を有する人材が課題解決には適任なのか。
- 順調に回っている業務はなんなのか、効率化の余地があるのか、はたまた円滑にできているように見えても生産性を定点で追ったらどう見えるのか。
- そもそも事業計画は本当に妥当な目標値なのか。そこにいる社員は疲弊していないか。
そういった実情がわからない中で、単にその事業の収支と、配置している人員数といった机上の数字をみて、じゃああと〇〇人増員するので、計画値をXX億円増やしましょう、とやっているのが事実。
しかもその計画値については事業部長と握るものの、ショートすることも多く、その場合でも人員を引き戻す等もせず送りっぱなしにしてしまっている現状。
必要な人員数を増員したのに、なぜ計画値が達成されていないのか。想定が甘かったのか、スキルアンマッチ者が発生しているのか。そういった原因の特定も実施できていませんでした。
そういった状況を打破するために、事業部に戦略人事機能を設けるべきだと考えたのが、現在の全社的なHRBP導入につながっています。
何から手をつけるべきか。羅針盤になったもの。
そこで私は、「事業戦略と連動した人事」を実現するためには、どのような取り組みをしていくのがよいのかについて考えました。正しくは、「自分はきっと井の中の蛙に違いない」「世の中の人事機能はおそらく先を行っているのではないか」と考え、他社の事例を探すことから始めてみました。
たくさんの本やインタビュー等を拝見する中で、唯一心の底から共感できるものがありました。
それが、現カゴメのCHOである有沢正人さんが書いた「カゴメの人事改革」という1冊の本でした。
有沢正人さんについて
有沢さんは、1984年に協和銀行(現りそな銀行)に入行し、業務の活躍を認められアメリカに派遣されMBAを取得、以降人事や経営企画業務に携わりつつ、その後2004年にはHOYAに入社し、全世界にまたがるグローバル企業においての人事統括を経験されてます。
その際、全世界共通の職務等級制度や評価制度を導入する等、人事制度構築で成果をあげられ、2009年に外資系保険会社であるAIU保険に、2012年にカゴメに特別顧問として招かれる等、日本では稀有な人事畑でキャリアを形成されている方になります。
企業の実情としての事例を理解したければ
先に挙げた著書に記載されているカゴメでの経験が特に私は印象に残っています。
- 海外の役職者を訪問し、目標設定シートを出せ、と言ったらその目標の内容が杜撰であったこと
- 経営層の後継者について管理/育成の仕組みが構築できていないこと
などなど。例を挙げるときりがありませんが、すべてが「うんうん、うちもそうだ」と思えるものだらけだったのです。
それぞれの課題に対して、例えばジョブ型制度に移行をかけたり、そこではジョブディスクリプションとして明確な目標を策定し社員にオープンにしていくことで、社員のキャリア自律の推進を図ったり、サクセッションプランの構築を推進したり・・・と、課題に対する打ち手とその導入時の問題点や周囲のリアクションから、手に取るように人事改革の難しさがわかります。
HRBPに関心を有する方や、既存の人事機能に疑問や課題を持っている方については、ぜひ有沢さんの著書を読んでいただきたいと思いますし、手に取ることで解像度がぐっと上がると感じています。
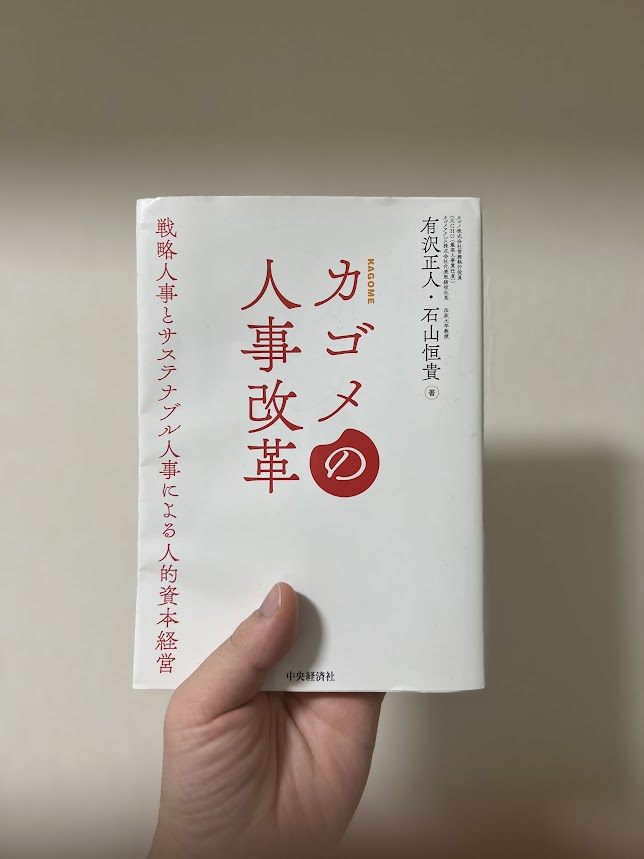
机上での検討ではなく、先行事例から学ぶこと、これができるのが後進者のメリットです。戦略人事に対する理解が広く促進され、現状に対する課題意識や何かしらのアクションにつながることを期待しています。
まだ読んだことが無い方はぜひお手にとっていただいてもいいかと思います。
カゴメの人事改革 戦略人事とサステナブル人事による人的資本経営戦略人事という観点では、以下記事でもまとめておりますので、よろしければご一読いただけますと幸いです。




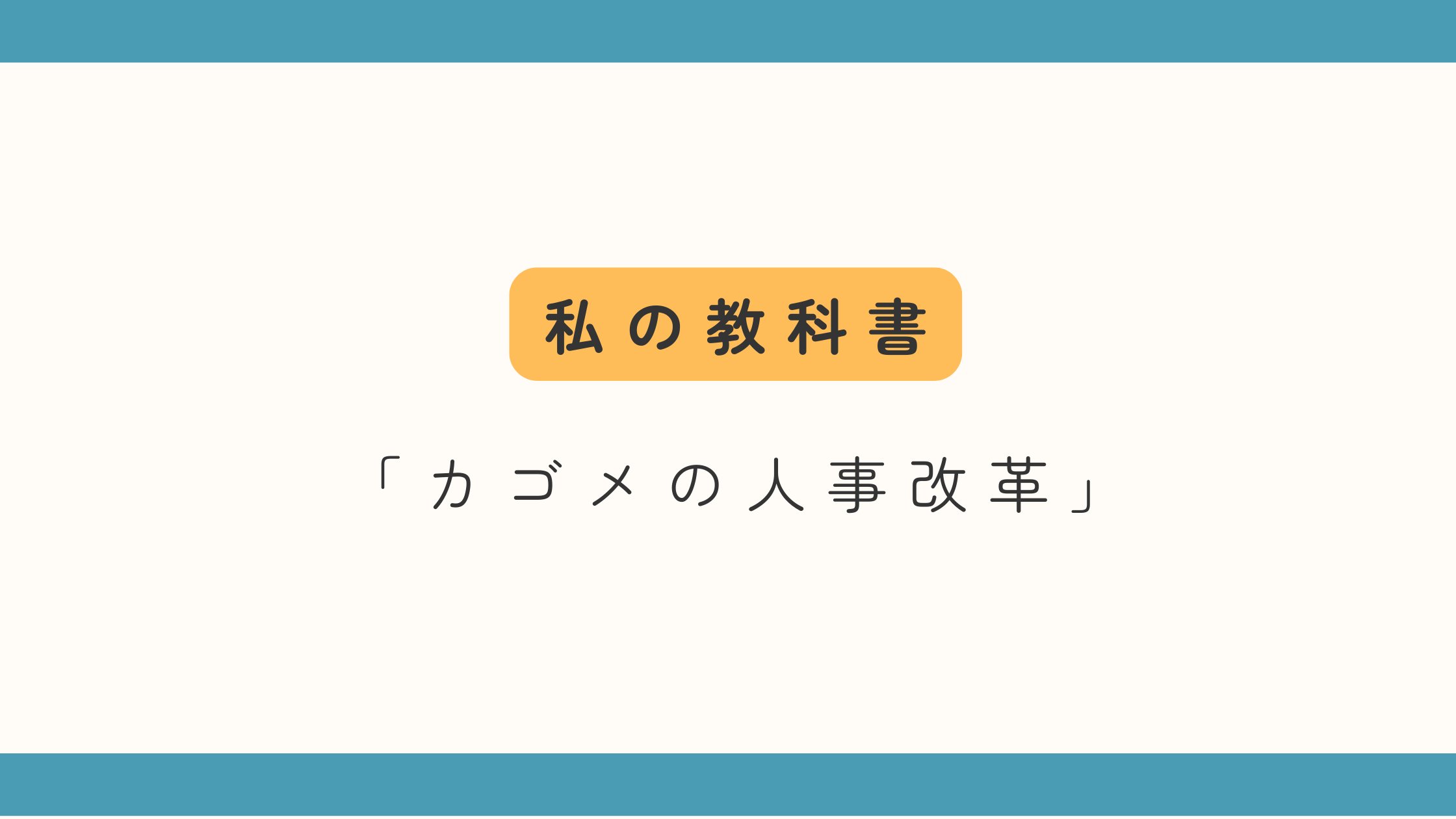



コメント