私はこれまで事業会社に所属し、事業の一線でキャリアを積んできましたが、縁あって3年前に当時の人事に呼んでいただき、現在は人事部で業務を実施しています。
今でこそチームを持ち、採用・育成・配置といったオペレーション業務や、抜本的な人事機能見直しに向けて一人称で取り組むことができていますが、着任した初年度、特に最初の半年間は、自分自身が何をすべきなのか全くわからず、ただただ周囲を見ながら真似したり、教わったりすることばかりで、戦力として貢献できた感覚は全くありませんでした。
ゆえに当時は自己肯定感が下がる一方で、「なぜ自分が人事に呼ばれたんだろう」「もっと適性ある社員がたくさんいるのではないか」そんなことばかり考えて、漠然とした不安や悩みを抱いていました。
だからこそ、人事部に異動して、初めて人事業務に取り組む方には、そもそも人事とはどのような業務なのかを前提として理解いただけると有意義だと考えています。巷には様々な書籍等もあると思いますが、実際に人事に身を置き経験をしてきたからこそ、真に役立つ思考のフレームについて整理してみました。
※私がどのような会社で、どのような人事機能を担っているかについては以下でまとめています。
「人事」は様々は役割から構成される”機能”である
一言で人事といっても、人事が担うべき役割は様々です。例えば以下のような役割があります。
会社人事と事業部人事(組織人事)
一般的には人事が設置される単位として、会社人事と事業部人事(組織人事)が存在します。
たとえば「営業部」「サービス開発部」「経営企画部」「総務人事部」…からなる会社が存在していたとしましょう。この場合、この会社に所属する全社員に対し必要となること、例えば処遇や福利、あるいは就業規則等を整備しているのは”会社人事”です。本例で言えば総務人事部がこの役割に該当します。
一方で企業の規模が大きくなればなるほど、会社人事において全社員の管理を担うことが難しくなってきます。そのため会社人事で担う機能や責任を再分担されたり、細分化されたりする観点で、事業部人事(組織人事)が設定されます。
例えば、昇格を例に考えてみましょう。昇格基準を考え選考を実施するのは会社人事で実施しますが、昇格の基準を満たす人を検討し選定するのは、各事業部人事が担います。
あるいは会社として業績が好調であり、営業部を強化したいため、若干名を増員したい、となった際に、営業部に配置すべき適性がある人を考え選定するのもまた事業部人事が担います。
勘の鋭い人であればお分かりになるかもしれませんが、事業部人事が担うのは、自組織に所属する社員に対し責任を持つ、ということなのです。人事目線の用語を用いるのであれば、自組織の社員の”人事管理”をしっかりやる、という一言につきます。
事業部人事は細分化される場合もある
このように、会社人事と事業部人事と大きく2つの機能があることはご理解いただけたかと思います。一方で先の例である「営業部」が、1000名の社員が所属する組織であり、主に自治体を主顧客とする第一法人営業部(700人)と、大規模企業を主顧客とする第二法人営業部という2つの組織に分類されていたと仮定しましょう。
その場合、第一営業部と第二営業部、それぞれに人事が設置されるケースも珍しくありません。自治体を攻略するために必要なフロントスキル、と、民需ユーザを攻略するために必要なフロントスキルは異なるため、それぞれが担う社員育成自体が異なることはイメージいただけるでしょう。
仕組みを整備する役割か、仕組みに基づき運用する役割か
次に、人事が持つべき機能についても考えます。
会社にどのような社員がいるかを冷静に考えてみると、部長や課長といった管理職の方もいれば、そうでない社員もいます。”そうでない社員”、といっても、一般的な企業では等級が定められているはずです。
たとえば入社時には総合職3級としてキャリアが始まり、昇格をすると総合職2級となり、さらに昇格すると総合職1級となり・・・というように、企業によって階段の数や名称は異なれど、この等級ごとに給与も紐づいているはずです。
つまにこういった等級制を整備している人事制度チームもいれば、ベース賃金や加算手当等に基づく社員処遇を所掌している給与チームもいるはずです。
もっといえばそういったものを、すべて言語化し、社員に公開するものとして社員就業規則というものがあり、本規則に対し責任を有するチームもあるでしょう。いずれにせよこういった仕組づくりを所掌する人事機能があるのです。
一方で、上記仕組がある前提で、社員のリスキリングやスキルの高度化を推進する人材開発チームもいるでしょう。あるいは育成や採用、人事異動や昇格を所掌するチームもいるでしょう。彼らは一言でいえば人事運用機能に位置付けられます。
前者の仕組みづくり側で言えば、雇用に係る法令に対する理解/精通度が求められたり、市場と自社の乖離等を確認する観点から他企業の人事制度に対する知見が求められます。このように仕組づくりを所掌する人事機能チームのベクトルは社外に対し向けられることも多いのが特徴です。
逆に運用側でいえば、一人ひとりの社員のキャリア形成を支援すつ観点から、彼らが描くキャリア像を理解し、現業における適性を図り、社員ごとの育成計画や配置替え等を検討・実行するなど、人事運用チームのベクトルは会社の社員に対して向けられます。
このように大きく分類すると、仕組を整備する機能と、人事を運用する機能の2つがあることについてご理解いただけたかと思います。
“人事”をマトリックスで理解する
ここまで記載してきた内容を基に、人事機能を分解したのが以下です。
| 会社人事 | 事業部人事 | |
|---|---|---|
| 仕組を整備する機能 | 就業規則や処遇等の人事制度を所掌 | 営業インセンティブ等、組織内に閉じた制度策定等を所掌 |
| 人事を運用する機能 | 人事開発、育成、配置、昇格等を所掌 | 組織内に閉じた育成や人材管理を所掌 |
初めて人事業務に従事する方は、自らがどの象限に位置するのか、最初に理解しておくことが重要です。なぜなら、いずれの象限に位置していたとしても、それ以外の象限を所掌するチームと密接な業務上の連携が発生するはずだからです。
例えばご自身が事業部人事の人事運用チームに該当する場合、おそらく様々な周知は会社人事の人事運用チームから落ちてくるはずです。
あるいは、あってはなりませんが、社員に懲戒処分を出したりする必要がある場合には、会社人事の制度チームに問い合わせをする必要があることでしょう。
このように各象限を所掌するのが、どの組織の誰なのか、を意識しながら業務に従事することで、必然的に組織理解が深まり、自らが求められる役割についても解像度があがることが期待できます。
ぜひ本象限を用いて、自身の位置づけを確認いただけると有意義だと思います。




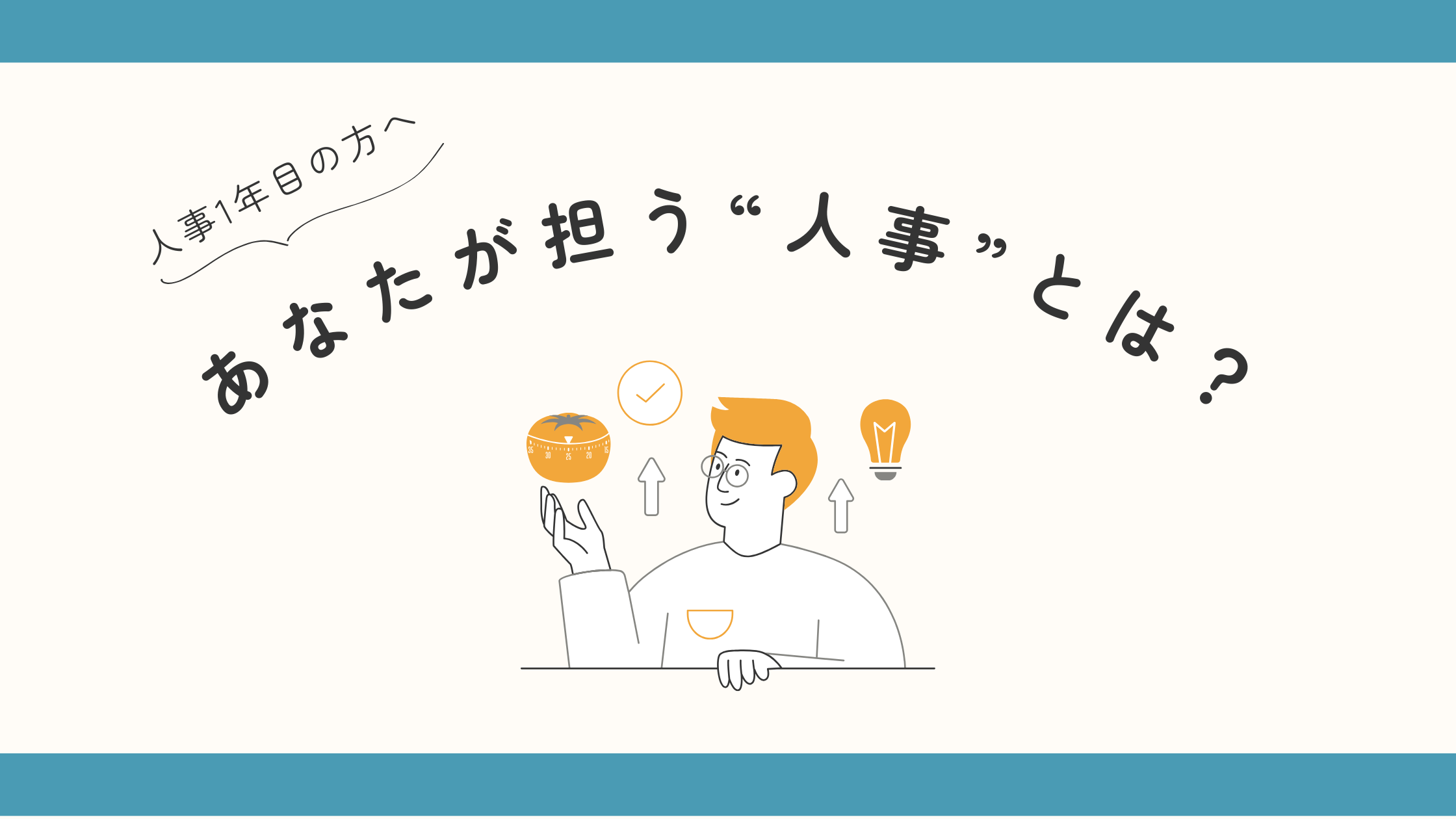



コメント