近年、HRBPを設置する企業が増えています。激しい市場競争の中で、自社の事業を維持・拡大するためには、社員という有限のリソースをどのように育てどのように事業に配置していくかを考え、機動的に対応していく役割が必要となります。
本記事では、HRBPという言葉が生まれた背景から、従来の人事との違い、HRBPがとるべき戦略に至るまで解説してきます。
HRBPとは
HRBPとは、「Human Resource Business Partner」の略称で、その頭文字をとって呼ばれます。
HRBPは企業の戦略的な人事機能を指し、従来の人事部門が担ってきた業務を遂行するのではなく、経営陣や事業部門と密接に連携し、組織の事業計画達成のためにあらゆる人事戦略を企画し、実行することが求められます。
HRBPが担う主の役割としては以下が挙げられます。
- 事業計画の達成に資するあらゆる人事戦略の立案・実行
- 事業を推進するプロフェッショナル人材の育成・獲得およびそのための人材管理
- 経営層と社員の仲介役(トップダウンの改革推進、ボトムアップの改善)
HRBPは経営層、具体的には組織長や事業部長の直下に置かれ、あらゆる事業上の課題を把握し、その解決に資する人材戦略の検討・実行を担います。組織の長の配下に置かれるのは、扱う課題の規模に捉われずタイムリーに必要な情報にアクセスできるようにするためであり、加えて組織の長とともに速やかにその対応方針を定め、実行に移すためです。
あらゆる人事戦略というと抽象度が高いので、少し嚙み砕いてイメージしてみましょう。
ときに、事業ごとの社員の配置数を大きく変革させる必要があるかもしれません。あるいは問題が顕在化していないものの、中長期を見据えたときに先行的に人材投資に舵を切る必要性が出てくるかもしれません。そういった際に意思決定をより早く円滑に実施するために、HRBPは経営層と常に連携する必要があるのです。

このように、HRBPとは事業部ごとに設置され、事業の長(事業部長)と常に課題認識を合わせながらトップダウン的な変革の推進を担ったり、ときに現場で起きている事象をエスカレしながら対応方針を事業部長と決定するなど、あらゆる役割を担うのです。
ここまで記載するとイメージが湧くかもしれませんが、いわゆる従来の採用活動や研修を展開するような”古くからの人事”とは明確に区別される機能であると言えます。
HRBPの誕生背景(起源)
そもそもHRBPという概念は、いつ頃誕生したのでしょうか?
遡ること1997年に出版されたデイビッド・ウルリッチ氏の「Human Resource Champions」(和訳『MBAの人材戦略』)において提唱された考え方と言われています。
その著書の中で、今後の人事部門が果たすべき役割として以下の4つが定義されています。
- HRBP(HR Business Partner)
- OD & TD(Organization Development & Talent Development)
- CoE(Center of Excellence)
- OPs(Operations)
HRBP以外にも3つの人事機能が定義されています。2つ目は組織開発・人材開発、4つ目は人事運用のオペレーション業務を指しています。3つ目は聞き慣れないワードですが、全社に係る人事のプロフェッショナル、とイメージいただけるとよいと思います。
つまりHRBPが担う「事業と連動する人事」を実現するためには、従来の人事が担ってきたオペレーション業務(労務業務や表彰・懲戒、研修や各種事務処理等の業務)から脱却し、全社の戦略人事機能(CoE)のもとで、各事業単位で組織や人材開発(OD&TD)に取り組めている状態を目指すべき、というのが本著書の内容です。
HRBPは常に事業の動向を踏まえ、何か課題はないか、目標までどれだけ過不足があるか、事業ごとの人材の余剰・不足状況はどうか等、考え続ける必要があります。そのため、稼働の多くを割くことになる人事運用業務等はHRBPは担うべきではないのです。
従来の人事とHRBPの違い
さて、HRBPは従来の人事とはどのような点で異なるのか考えてみましょう。
これまで各社が各組織ごとに設置してきた人事は、主としてその当該組織に属する社員が、効率的に・健康的に業務に従事できるよう、社内の環境や制度を整備することが主の業務であったはずです。一方でHRBPは、事業計画達成のために事業部長の直下に置かれ、課題認識を共通化し、日々あらゆる戦略を立て実行することが求められる点で異なるのです。
表でまとめると、以下のように違いが明確化されます。
| 人事 | HRBP | |||
|---|---|---|---|---|
| 役割 | 事業課題の発見、解決に向けた人事戦略の立案・実行 | 人事制度の整備、制度に基づく人事運用 | ||
| 業務内容 | (ルーティーン業務は担わず)自ら検討の上決定 ※日々流動 | 給与管理 労務対応 表彰懲戒 等 | ||
| チーム編成 設置単位 | 部長、課長(+係長) 事業部長直下に設置 | 課長、係長、担当者 等 組織内に人事ユニットを設置 | ||
| スタンス | 攻めの人事(企画や戦略建てに頭を使う) | 安定的な人事運用(効率的なオペレーション) | ||
※スマートホンの方で見切れてしまう場合には横スクロールで確認ください。
HRBP=HRビジネスパートナーであり、事業パートナーです。人事部という組織に所属し事業を外から眺めるのではなく、事業組織の中に身を置くことで課題を我が事化し、その解決自体が自身のミッションであるという点をよく理解しておく必要があります。
HRBPが担うケーススタディ
さて、ここまで読んでくださった方は、HRBPというのは新たな概念で、事業計画達成のために何でもやる人、というイメージを持っていただいたのではないかと思います。そのイメージをより具体化するために、以下ケースを用意しました。HRBPであればどのような対応をとるのか、想像しながら考えてみましょう。
ケーススタディ
みなさんはある事業のHRBPです。所属している事業の状況として以下を想像してください。
・今年度、利益ベースで10億円の事業計画を立て取り組んでいるところ
・現在上期(半年)が終了し、達成状況は4億円の状況で、下期に6億円の達成が必要
・本事業に従事している社員は8名。他部署も計画達成に苦戦している状況。
上記ケースがあった場合に、みなさんなら下期リカバリー策をどのように考え、実行するでしょう。
案①:本事業に増員する
ある人は、人員数を8名から増員すればいい、と考えるかもしれません。一方で他の部署も計画達成に苦戦しているため、その事業から人を剥がし、この事業に配置替えすることは容易ではありません。
仮に増員での対応を検討するのであれば、現状の1名あたりの生産性を事業ごとに算出し、他事業と比較して本事業の生産性が高いことを根拠として実施する必要性が出てくるでしょう。
例えば本事業は8名の社員で4億円の利益を創出しているため、1名あたり0.5億円の利益を生んでいることになります。一方で、他事業では1名あたり1億円の利益を生み出しているかもしれません。その場合他事業から人をはがし本事業に人を持ってくることはかえって会社の事業計画達成に逆行する動きとなります。
あるいは新卒や中途で人材を市場から獲得する方法もあります。
一方で、新たに雇用した社員が即戦力として速やかに活躍することは稀有でしょう。会社や組織、あるいは業務フローに対する理解を深めてもらうために、周囲の社員が支援する必要性があります。つまり、新たに社員を雇用することは、周囲の社員の生産性を落とす可能性も考慮しておく必要があります。もっといえば会社としては人件費が増加することも念頭に置く必要があります。人件費以上の利益を創出してくれるであろう確からしさがないと、かえって事業の生産性を落とすことになるかもしれません。
次年度以降も販売計画が拡大する前提であれば、目先の即戦力としての中途採用よりも、今から労力をかけて新卒採用社員を獲得したほうが有意義な可能性もあります。
HRBPは上記のように課題に対し多岐に渡る手段を検討し、打ち手の根拠や期待度を可視化・比較し、とるべき選択を示し実行する役割を担うのです。
案②:社員のスキルを向上させる
では別の案を考えてみましょう。8名で4億円の利益といっても、売り上げが高く販売に長けた社員もいれば、まだ成長の余地が多分にある社員もいたりと、ばらつきがあるはずです。
高い成果を出している社員にあって、その他の社員にはないスキルは果たしてどのようなものがあるでしょうか?
営業としてのヒアリング力、提案資料や見積もりを作成する能力、ユーザとのコミュニケーション能力、社内のアセットや組織に対する精通力、テクニカル面も含め課題解決できる提案力・・・
考えるだけでも多様な要素に分解できます。
例えば営業として求められるスキルを定義し、一人ひとりの達成状況を可視化し、個々人ごとの育成プランを立てることが、生産性向上につながり、さらには販売状況が大幅に改善される可能性もあります。
課題に対するアプローチ策を常に検討・実行する
上記ケーススタディで例示したように、課題に対して取りうる選択肢や検討は多岐に渡るため、HRBPは必ずこれを実行しなければならない、というものはありません。HRBPは事業動向を理解し、あらゆる人事戦略を考え実行するのがミッションです。そのため人材の獲得も育成も全てがミッションであり、その必要性を幹部や関連部署と議論し合意をとり、実行することまで求められるのです。
従来の人事であれば、事業側の幹部からの要請に基づき、採用計画を見直したり、引き合いに応じて配置すべき人材を考えていたかもしれませんが、HRBPはそれを他人事とせず自らの役割と責務において実施しなければならない点で従来の人事とは異なる、ということについてご理解いただけたと思います。
机上での検討から学ぶことも多い一方で、実際に導入している企業から学ぶことは更に貴重で有意義なものです。以下記事では、HRBPを実際に導入している企業について取り上げていますので、併せてご確認いただけますと幸いです。




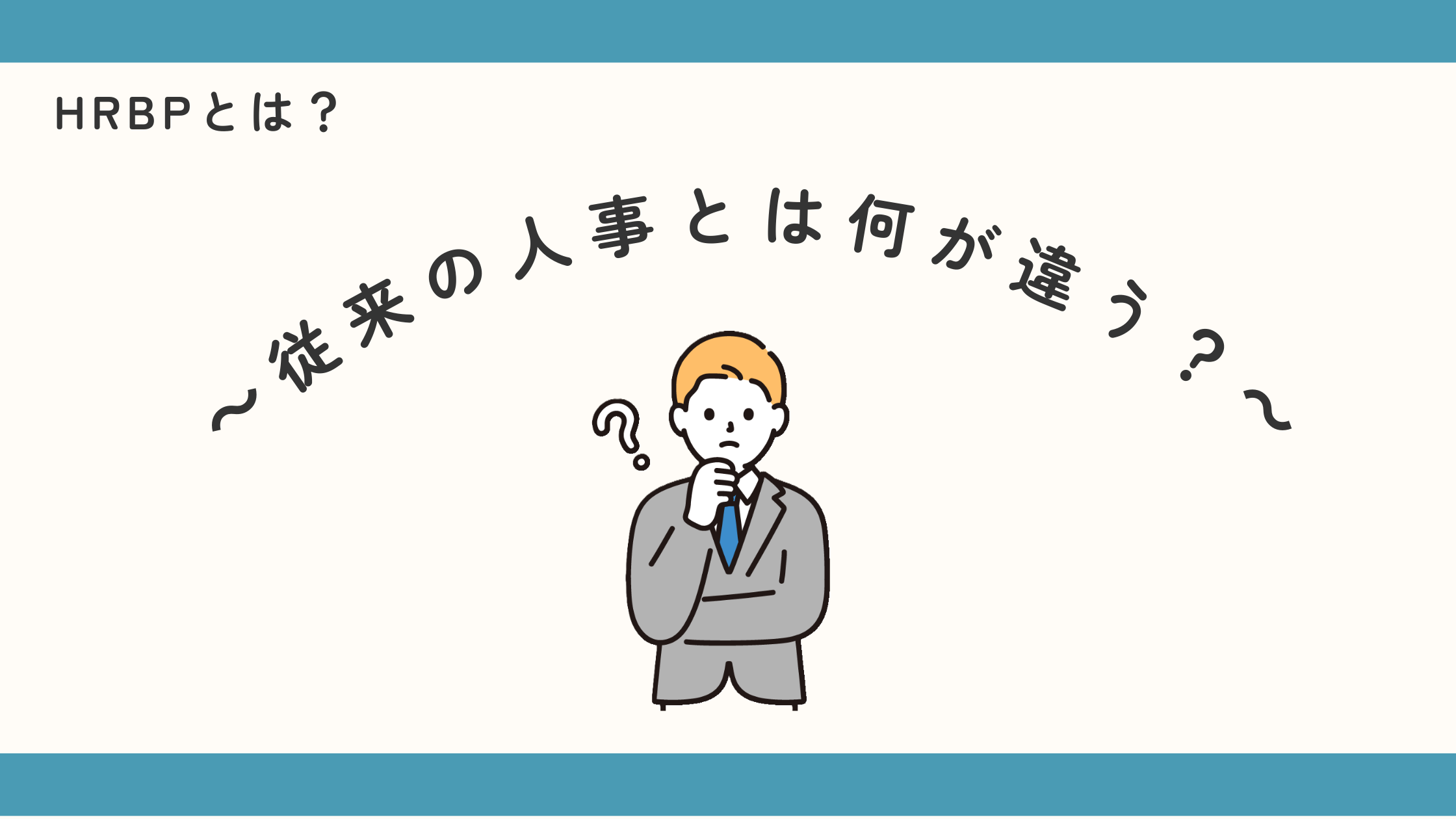

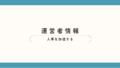

コメント