HRBPは事業ごとに設置され、その事業の計画達成に向けたあらゆる人事戦略を企画・実行する役割を担います。ここでは、HRBPを導入している代表的な企業として、2社を取り上げます。
実際のHRBPの方々はどのような取り組みをしているのか、具体的な事例を通じて理解を深めましょう。ちなみにここで取り上げる2社については、私自身も双方のHRBPの方々と意見交換をさせていただいたことがあり、HRBPが能動的かつ機能している会社だという印象があります。
※HRBPとは何か、いわゆる”人事”とは何が異なるのかについては、以下の記事でまとめていますので、基礎的なところから理解したい方は、まず以下をご確認いただけると良いと思います。
日立製作所
導入時期と導入背景
日立製作所は、2021年4月にHRBP体制を正式に導入しました。この時期は、同社がジョブ型雇用への移行を本格化させたタイミングでもあり、HRBPの導入はグローバル化の進展や多様化する事業環境に対応するため、従来の人事管理手法から脱却し、より戦略的な人事マネジメントを実現するうえで重要な役割を担っていました。
日立は、2009年頃にリーマンショックの影響を受け、約7000億円を超える赤字を計上しています。その際にグローバル事業への大幅な転換や事業再編を行う必要性があり、それを実現するための社員育成や配置を事業単位で我が事化できる人材を作るために、人事機能の見直し要請が強まった、と以前日立の方から伺ったことがあります。
具体的な役割例
事業部長直下での課題解決
日立の事業領域は、ITやモビリティシステム、原子力ビジネスに至るまで多岐に渡ります。そのためHRBPは、ビジネスユニットごとに設置されています。事業部長と密接に連携し、事業戦略に基づいた人事戦略を自ら企画し、実行することで事業目標の達成を支援しています。たとえば、事業部の事業計画を達成するために、収益が好調な事業と、そうでない事業を明らかにし、その課題に注目しながら社員をより収益の高い事業にシフトさせたり、あるいは社員のスキルを高めるための育成などあらゆる対応を行います。
タレントマネジメントの推進
HRBPは自組織にいる多くの社員について、誰よりも理解している必要があります。具体的には上述の通り、事業領域が多岐にわたるため、事業ごとに求めるスキルも異なってきます。そのため、全社員共通的に必要となる資質についてはCoE(会社人事)主導で整理をし、事業ごとに必要となるスキルは事業ごとに検討の上定義をしています。
そのスキルレベルを基に社員一人ひとりの到達点を評価し、キャリア目標を策定したり適切な配置や育成プランを策定しています。また、日立では社員エンゲージメントも経営上の重要な指標となっているとのことで、HRBPは自事業部社員のエンゲージメント向上を図るための課題抽出や施策の実行等も担っています。
事業課題にひたすら向き合う(人事運用に逃げない)
また日立の方と話していて最も印象に残っているのは、事業課題にしっかり向きあうということです。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、普段社員が事業をしている中では様々な人事上の対応が発生します。こうした人事運用に対応していると、日々の業務稼働の割合を割かれ、本来HRBPとして実施するべき、頭を使って事業課題に向き合い、対応について悩み検討し、打ち手をひたすら実行していく、ということができなくなってしまいます。
そのためHRBPは本来業務に稼働を費やすことが重要であり、その意味では人事運用は本来実施すべきメンバーと連携しながら対応することで、総体的にチームを機能させているのです。
導入後の効果について
HRBP導入による効果として、以前日立の方から以下を伺いました。
- グローバル事業へのシフトが加速化し、現在の収益の一定割合はすでにグローバル事業が牽引
- 適所適材等の推進により、直近の社員エンゲージメントも向上
- 事業課題に対し戦略人事をもって対応していくことができている
日立はHRBPを担う人材に対する研修等も実施していると聞いており、日本を代表するHRBP導入企業であると私は考えています。
ディー・エヌ・エー(DeNA)
導入時期と導入背景
ディー・エヌ・エー(以下、DeNAと記載)は、2014年にHRBPの導入を行っています。当時はゲームやEC事業を中心としたビジネスモデルから、ヘルスケアやオートモーティブといった新規事業の展開を加速化しているフェーズであり、多角化する事業に対し、各事業部門の特性に応じた柔軟な人事戦略が求められるようになったことが導入の背景です。
また新規領域での事業展開を進めるにあたっては、異業種からの転職者が増加している状況もあり、DeNAの文化を伝承しながら組織づくりをしていく機能としても、HRBPに白羽の矢が立ったようです。
HRBPがやること、やらないこと
HRBPについては、組織戦略から人員計画の策定、採用、研修、組織開発まで、すべての人事課題をHR本部と連携して解決していく役割を担わせています。
一方でHRBPが「やらないこと」として、給与計算や人事規程の作成、新卒採用等を定義し、HRBPが本来どの領域に稼働を費やすべきかを明確化しています。
HRBPにすべてを期待するのではなく、会社人事がやることとHRBPがやることを明確に区分けし、HRBPが本来稼働を費やすべき領域を定義していること、これがDeNAにおいてHRBPが機能している仕組のように思います。
またDeNAは自社のHPにおいてもHRBPについて記載をしており、やはりHRBPが本業に専念できるよう支援していることがわかります。
HRBPの役割
多様な事業を持つDeNAでは、事業ごとにビジネスモデルも違えば、必要とされる人材の特性、さらに言えば発生する課題も多岐に及びます。そのため、2014年に事業部ごとの人事戦略を担うHRBP(HRビジネスパートナー)を設置しました。労務や給与計算、新卒採用全般といった全社共通の人事を司るHR本部があり、各事業部ごとにHRBPがいる構造にしています。HR本部全体が長期的に会社の文化や基礎を高める役割を担い、HRBPが各事業部が抱える課題を人事的な観点から解決し、事業が成長するための環境を整えます。
HRBPは事業戦略にもとづいて、事業部門の責任者に対し人と組織の両面からサポートを行い、事業成果に貢献します。
出典:https://csr.dena.com/jp/employees/hr-strategy/
導入後の効果について
HRBPが機能していることで、以下のような成果を創出しています。
採用の効率化
HRBPは事業を維持・拡大していくために人材を獲得することも重要なミッションの1つです。それを裏付けるエピソードとして、リファラル採用の強化があります。HRBPが事業部内に入り込み、リファラル採用を強化したことで年間相当数の人材を中途採用として採用することに成功しています。
エンゲージメントの向上
社員一人ひとりのキャリア形成支援を行うことで社員のエンゲージメントスコアの向上に寄与しています。もはや上述の日立と同様、社員エンゲージメントは経営上注視すべき指標であり、エンゲージメントの向上や数字の裏に隠された課題把握など、事業と社員と向き合うHRBPだからこそ実施できる領域なのかもしれません。
また、DeNAはHRBPの機能について、積極的にオープンしている印象があります。HRBPの方々に対する様々なインタビュー記事や、HRBPの方が担うミッション等、広く情報を発信しており、日本を代表するHRBP導入会社といえるでしょう。
HRBPが機能するカギとは
HRBPを設置したからといって、事業が変化することはありません。大切なのはHRBPという役割に、どのような目標を持たせるか、どういった人材をHRBPとして配置するかがカギです。
その意味では、すべての会社にHRBPを設置する必要性はないでしょう。すでに各組織にいる人事が能動的に同じ機能を果たしているかもしれません。あるいは事業が単一の会社については、トップダウンでコントロールが効く場合もあります。
HRBPが機能するカギは、現状起きている課題や不足する機能をしっかり議論し、自社において必要なHRBP像のペルソナを設定することです。
その中では各社のHRBPの取組を参考にすることは有意義であると考えています。





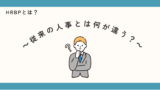


コメント